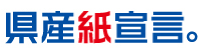長崎原爆が投下される前日の1945年8月8日。私が学童疎開していた西彼大草村(現諫早市多良見町)に、母が長崎市内から訪ねてきた。その2日前は私の誕生日。母は身重の体でわざわざ祝いに来て、「何があっても手放さないように」と私の通帳と印鑑を手渡してくれた。
私は寂しくて「長崎に帰らないで」と頼んだが、母は幼い弟たちが待つ長崎へ戻っていった。あの時、引き留められれば母は原爆に遭わなかったのに-と今も悔やむ。
長崎で被爆した父や、疎開先の大草から救援に向かった姉によると、母は爆心地から500メートルの城山地区で洗濯物を干している時に被爆した。爆風で吹き飛ばされた衝撃で死産。それでも亡くなった赤ちゃんを抱え、はうように自宅へ戻り、父や姉と再会したそうだ。
長崎の自宅に残っていた兄と姉、5歳の弟は頭や腕、脚のない「だるま」のような状態で見つかり、わずかに残った服の切れ端でそれぞれ誰か分かった。工事現場にいた父は原爆の閃光(せんこう)が走った瞬間、近くにあった砂山に頭を突っ込み意識を失ったが、大きなけがはなかったという。
原爆投下の数日後、大草に運ばれてきた母は、全身が黒く焼け、無数のガラスの破片が突き刺さり、傷口にはウジが湧いていた。薬もなく、治療はできなかった。
それでも母は私の名前を呼び、私を触ろうと手を伸ばした。しかし私は、数日前に会った母とはあまりにかけ離れた姿に驚き、泣いてばかり。姉からは「怖がらないで笑顔で看病しなさい」と叱られたが、私は「これはお母さんじゃない」と思った。お化けのような“物体”を前に、私は触れることも近づくこともできなかった。
終戦翌日の16日深夜、母は息を引き取った。母が寝ていた布団やその下の畳は、体の形に変色していた。近くには火葬場がなく、自分たちで拾い集めた木々を組み上げて燃やし、母を荼毘(だび)に付した。9歳になったばかりの私には堪えがたい光景。「一緒に死にたい」と火に飛び込もうとしたが姉に止められ、泣き続けた。なかなか灰にならず、丸一日かかったが、最後はわずかな骨が残った。
8月19日から6日間、家族で長崎市中心部を訪れ、自宅周辺を訪れたり、母の遺骨を墓に入れたりした。私が入市被爆したのはこの時だ。