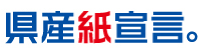1945年の春まで、長崎市竹ノ久保町1丁目(当時)に両親や5人のきょうだい、お手伝いさんと一緒に暮らしていた。父は多くの従業員を抱える建設会社を営み、自宅は当時としては珍しいコンクリート造り。母のお腹には秋に産まれる予定の新しい命が宿っていた。
しかし自宅周辺は、空襲による火災の延焼などを防ぐため強制的に取り壊される「建物疎開」の対象になった。近くに変電所(九州配電竹ノ久保変電所)や軍需工場があったためで、私は「変電所が攻撃されないように」と聞かされていた。疎開で自宅を失ったが、父が軍の仕事を請け負っていた関係で、城山地区の宿舎に一家で移り住んだ。
さらに空襲が激しくなり、登校中の児童が巻き込まれて亡くなる事態も起きた。姉と兄、私の3人は両親や他のきょうだいを長崎に残し、西彼大草村(現諫早市多良見町)の知人宅へ逃れた。45年5月ごろのことだ。私は大草村国民学校の3年生、兄は6年生として転校。姉は東京の医科大に合格して医師を目指していたが、夢を諦めて同校の臨時教員となった。
8月9日は朝から、避難させてくれていた知り合いのおじさんと山に登り、物資不足の中で「飛行機の燃料になる」と言われていた松やに(マツの樹脂)を採っていた。
木々の間から突然、ピカッと強い光が差し、ドーンと地響きが聞こえた。長崎の方角を見ると、山の向こうに白っぽい大きな雲がモクモクと上がり、その後黒く変わった。しばらくすると長崎方面の空は昼間なのに赤く染まり、「夕焼けみたい」と感じた。
おじさんに手を引かれて山を下り、自宅でラジオのスイッチを入れたが、なぜか電波が入らなかった。周囲の大人たちも「何事だろう」と不安がっていたが、詳しい情報はなく、長崎に残っている両親やきょうだいの安否も分からなかった。姉は翌10日の朝から、地元の消防団員と一緒に列車の線路沿いを歩いて長崎へと向かった。
数日後、姉は何とか父と母を捜し出し、大草へ連れ帰ってきた。他のきょうだい3人やお手伝いさんは、城山の宿舎で「即死」したという。父は自分で動けたが、担架に乗せられた母は全身が黒く焼け焦げ、前後の見分けも付かないほど。辛うじて生きていたが、その姿が恐ろしくて近づくことができなかった。