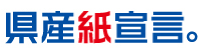長崎刑務所(諫早市)は2022年10月から知的障害(疑い含む)のある受刑者の特性に応じた処遇を図る事業に取り組む。同事業は国のモデル事業で5カ年計画。犯罪を繰り返す「累犯障害者」の支援に長年携わる南高愛隣会と協力して始め、2年が経過した。今年6月には、懲役刑と禁錮刑を「拘禁刑」に一本化する改正刑法が施行される。刑務作業を義務とせず、特性に合わせた柔軟な処遇の実現を目指す。立ち直りや社会復帰を支援する処遇の現場を取材した。
「福祉」に抵抗感
「皆さん、仕事をする上での悩みはありますか?」
昨年11月、長崎刑務所(諫早市)。長崎障害者就業・生活支援センター(社会福祉法人南高愛隣会が運営)の所長が尋ねると、受刑者が次々に手を挙げ、意見を述べた。
「面接を受けても就職につながりません」
「仕事が続きません」
この日、5人の受刑者が受講していたのは福祉制度学習。「福祉」に抵抗感を示す受刑者が少なくない実態を受け、正しい理解を促すため、昨年7月に始まったプログラムだ。
同センターの職員が就労支援や生活保護など福祉制度について図を用いながら丁寧に説明。「できないことがあると思いますが、私たちが相談に乗ります。一緒に考えていきましょう」。このプログラムの他に出所半年前にも同じ内容の説明を行い、福祉の大切さを繰り返し伝えている。
「刑務所が学びの場」
国のモデル事業の対象者は2024年12月時点で延べ65人で、九州内の刑務所でスクリーニングツールを用いて選考している。
能力に応じてコースを選定。▽一般企業への就労を目指す「ビジネスサポート」▽農園芸作業などを通して就労継続支援事業所につなげる「福祉的就労」▽和太鼓や絵画で自己表現を図る「福祉サービス利用」-の3コースに分かれ、4カ月の訓練を受ける。約7割が福祉的就労コースを受講しているという。
対象者のアセスメント(評価)や刑務作業の指導に関わる作業療法士、池田友美(仮名、49)は「幼少期に適切な学習機会がなかった人が多く、刑務所が学びの場になっている」と指摘。できるところをほめて自己肯定感を高め、立ち直りに向けた動機づけの向上を目指している。
昨年12月に同刑務所であった事業の中間報告会でも、対象受刑者への聞き取り調査から自己肯定感の上昇といった「一定の効果」が示された。視察した福岡高検検事長の松本裕は「(モデル事業は)先取りして拘禁刑の在り方を形づくっていく取り組み。見えてきた課題について検察としても一緒に考えていきたい」と述べた。
「自分が知的障害者という認識はなく…」
福祉制度に対する受刑者の理解が進んでいる兆しも見える。侵入盗の罪で入所した前川重敏(仮名、57)は、今回が11回目の服役。仕事に就いても人間関係でつまずいて辞め、貯金が底をついたタイミングで窃盗を繰り返してきた。10代の頃、親の申請で療育手帳は取得していたが、使い道は知らないまま。「自分が知的障害者という認識はなく、今まで福祉の『ふ』の字も出てこなかった」と言う。
今回、プログラムで福祉制度を学び「(利用できる制度が)あるなら利用したい」と前向きに捉えた。出所後は更生保護施設に入り、就労継続支援事業所を利用することを希望し「周囲に相談しながら生きていきたい」。
「百八十度違う」
職員には戸惑いも見え隠れする。35年目のベテラン刑務官、古川憲一(仮名、57)は「これまでの指導のやり方と百八十度違う。積み上げてきた意識を変えることは大変」と明かす。社会復帰に向け、以前は厳しさ一辺倒だったが、今後は「支える」意識が強く求められるとした。
帰住先の調整に携わる福祉専門官、前田夕喜(仮名、45)は新たな課題として「(知的障害に)発達障害を持ち合わせているような受刑者もみられる」と現場の感覚を表した。強いこだわりを持っている場合が多いとし、池田も「自分の当たり前が社会の当たり前ではないということを伝えることが難しい」と語った。
モデル事業は26年度までの5カ年計画で効果を検証し、全国展開を検討する。同刑務所社会福祉支援部門の首席矯正処遇官、平川勝文(49)は「出所後も息の長い支援をするためにも、帰住先の確保が重要になってくる。地道に情報を発信し、支援機関との連携推進や拡大に努めたい」としている。
「福祉」に抵抗感
「皆さん、仕事をする上での悩みはありますか?」
昨年11月、長崎刑務所(諫早市)。長崎障害者就業・生活支援センター(社会福祉法人南高愛隣会が運営)の所長が尋ねると、受刑者が次々に手を挙げ、意見を述べた。
「面接を受けても就職につながりません」
「仕事が続きません」
この日、5人の受刑者が受講していたのは福祉制度学習。「福祉」に抵抗感を示す受刑者が少なくない実態を受け、正しい理解を促すため、昨年7月に始まったプログラムだ。
同センターの職員が就労支援や生活保護など福祉制度について図を用いながら丁寧に説明。「できないことがあると思いますが、私たちが相談に乗ります。一緒に考えていきましょう」。このプログラムの他に出所半年前にも同じ内容の説明を行い、福祉の大切さを繰り返し伝えている。
「刑務所が学びの場」
国のモデル事業の対象者は2024年12月時点で延べ65人で、九州内の刑務所でスクリーニングツールを用いて選考している。
能力に応じてコースを選定。▽一般企業への就労を目指す「ビジネスサポート」▽農園芸作業などを通して就労継続支援事業所につなげる「福祉的就労」▽和太鼓や絵画で自己表現を図る「福祉サービス利用」-の3コースに分かれ、4カ月の訓練を受ける。約7割が福祉的就労コースを受講しているという。
対象者のアセスメント(評価)や刑務作業の指導に関わる作業療法士、池田友美(仮名、49)は「幼少期に適切な学習機会がなかった人が多く、刑務所が学びの場になっている」と指摘。できるところをほめて自己肯定感を高め、立ち直りに向けた動機づけの向上を目指している。
昨年12月に同刑務所であった事業の中間報告会でも、対象受刑者への聞き取り調査から自己肯定感の上昇といった「一定の効果」が示された。視察した福岡高検検事長の松本裕は「(モデル事業は)先取りして拘禁刑の在り方を形づくっていく取り組み。見えてきた課題について検察としても一緒に考えていきたい」と述べた。
「自分が知的障害者という認識はなく…」
福祉制度に対する受刑者の理解が進んでいる兆しも見える。侵入盗の罪で入所した前川重敏(仮名、57)は、今回が11回目の服役。仕事に就いても人間関係でつまずいて辞め、貯金が底をついたタイミングで窃盗を繰り返してきた。10代の頃、親の申請で療育手帳は取得していたが、使い道は知らないまま。「自分が知的障害者という認識はなく、今まで福祉の『ふ』の字も出てこなかった」と言う。
今回、プログラムで福祉制度を学び「(利用できる制度が)あるなら利用したい」と前向きに捉えた。出所後は更生保護施設に入り、就労継続支援事業所を利用することを希望し「周囲に相談しながら生きていきたい」。
「百八十度違う」
職員には戸惑いも見え隠れする。35年目のベテラン刑務官、古川憲一(仮名、57)は「これまでの指導のやり方と百八十度違う。積み上げてきた意識を変えることは大変」と明かす。社会復帰に向け、以前は厳しさ一辺倒だったが、今後は「支える」意識が強く求められるとした。
帰住先の調整に携わる福祉専門官、前田夕喜(仮名、45)は新たな課題として「(知的障害に)発達障害を持ち合わせているような受刑者もみられる」と現場の感覚を表した。強いこだわりを持っている場合が多いとし、池田も「自分の当たり前が社会の当たり前ではないということを伝えることが難しい」と語った。
モデル事業は26年度までの5カ年計画で効果を検証し、全国展開を検討する。同刑務所社会福祉支援部門の首席矯正処遇官、平川勝文(49)は「出所後も息の長い支援をするためにも、帰住先の確保が重要になってくる。地道に情報を発信し、支援機関との連携推進や拡大に努めたい」としている。