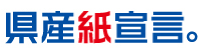長崎市の野母崎地区で海洋保全などに取り組む市民グループ「team長崎シー・クリーン」(出水享代表)が、昨秋から廃棄野菜を餌にムラサキウニを養殖している。磯焼けで海中の海藻は減少しており、野母崎三和漁協は海藻を餌とするウニの駆除作業を定期的に実施。同グループは、同漁協とJA全農ながさきとのコラボで、ウニと廃棄野菜の活路を見いだそうとしている。
ウニ漁師で、同漁協の馬場広徳筆頭理事によると、磯焼けは地球温暖化による水温上昇や水質変化などが影響。海藻減少により、魚類の産卵場所が減っているほか、餌がないためウニの身入りが悪くなっている。
また海中のウニの生息数は1平方メートル当たり2~3個が最適とされるが、同地区沿岸では20~30個と繁殖能力が高い。同漁協はウニ駆除で海藻が生えてきたとの研究結果を基に、毎年範囲を区切り、1週間に渡って毎日2万個以上を駆除し続けているが、海藻は依然増えず、商品にならないウニが増える一方という。
これを受け、同グループの出水代表はJA全農ながさきとのコラボを企画。変色や形が悪いなどの理由で出荷できなくなった複数の廃棄野菜を譲り受け、昨年11月から海中で養殖するウニの餌とする取り組みを始めた。大根を餌としたウニは水っぽく、ニンジンは苦みがあり、ブロッコリーが一番おいしく仕上がったという。
現在は2週間おきに、ウニ約30個が入ったカゴにブロッコリー約900グラムを与えている。中心メンバーの内野由希子さん(45)は「餌の量や頻度は水温などを見て調整する必要があり試行錯誤。身入りをよくするため継続して工夫したい」、出水代表は「地域の特産になれば」と話している。
ウニ漁師で、同漁協の馬場広徳筆頭理事によると、磯焼けは地球温暖化による水温上昇や水質変化などが影響。海藻減少により、魚類の産卵場所が減っているほか、餌がないためウニの身入りが悪くなっている。
また海中のウニの生息数は1平方メートル当たり2~3個が最適とされるが、同地区沿岸では20~30個と繁殖能力が高い。同漁協はウニ駆除で海藻が生えてきたとの研究結果を基に、毎年範囲を区切り、1週間に渡って毎日2万個以上を駆除し続けているが、海藻は依然増えず、商品にならないウニが増える一方という。
これを受け、同グループの出水代表はJA全農ながさきとのコラボを企画。変色や形が悪いなどの理由で出荷できなくなった複数の廃棄野菜を譲り受け、昨年11月から海中で養殖するウニの餌とする取り組みを始めた。大根を餌としたウニは水っぽく、ニンジンは苦みがあり、ブロッコリーが一番おいしく仕上がったという。
現在は2週間おきに、ウニ約30個が入ったカゴにブロッコリー約900グラムを与えている。中心メンバーの内野由希子さん(45)は「餌の量や頻度は水温などを見て調整する必要があり試行錯誤。身入りをよくするため継続して工夫したい」、出水代表は「地域の特産になれば」と話している。