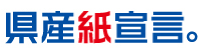今どきの子どもがどうなのかは、よく知らない。小さいころ、太陽を描く時は決まって赤く、月は黄色に塗っていた。これが欧米だと太陽は黄色、月は白色に描くという▲色にまつわる“常識”は国それぞれと思ったら、日本の古人も月を白色と見ていたらしい。百人一首に坂上是則(さかのうえのこれのり)が詠んだ歌がある。〈朝ぼらけ有明の月と見るまでに吉野の里に降れる白雪〉。明け方、有明の月と思うほど吉野の里に白々と雪が降っている、と▲昼間は炎天が収まらないが、夜は月が明るい季節になった。古人の気持ちで“白い月”をめでるのもいいかもしれない。おとといは中秋の名月、きのうは十六夜(いざよい)の満月だった▲満月は次第に欠けながら、日に日に何十分か遅れて出るようになる。きょう十七夜の月は立っていると現れる「立待月(たちまちづき)」、あすの月はゆっくり座って待つ「居待月(いまちづき)」と、月の出に合わせて見る人の姿や行動も変わる▲その翌日は横になって待つ「臥待月(ふしまちづき)」、その次はすっかり夜も更けて「更待月(ふけまちづき)」。日ごとに立って、座って、寝て、あくびをしながら月を待つ。美しく輝き、人を引きつける月を「待」の1字が表すようでもある▲その日を少し過ぎたが、芭蕉の有名な一句を。〈名月や池をめぐりて夜もすがら〉。夜どおし眺めた月はさて、何色に映ったのだろう。(徹)
白い月
長崎新聞 2024/09/19 [10:00] 公開