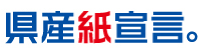最大震度7の能登半島地震で始まった2024年は、自然の脅威を思い知らされる1年となった。いつどこで起こるか分からない自然災害。長崎県南島原市にある泉川病院の災害医療派遣チームは、24時間365日対応できるように準備を続けている。被災現場に立つ怖さはあるが、誰よりも早く困っている人の元へ。突き動かすのは「救いたい」という医療人の本分だ。
11月下旬、病院を拠点に大規模災害を想定した訓練が抜き打ちで行われた。各職場で働く隊員を招集。薄暗くなった午後5時過ぎに始まった。駐車場に用意された現場は、がれきの山。崩れた屋根の下に取り残された人を救出するという能登の現場で遭遇したシチュエーションだった。
午後9時ごろ、夕飯を終えると雲仙の山中に移動。道路が寸断され、取り残された負傷者を担架で運び出す訓練で、ヘッドライトの明かりだけを頼りに山道を進んだ。気温3度。霧も深まり、日付が変わるころに終了した。病院に戻って駐車場でテント泊。訓練は3日間続いた。このような2泊3日の厳しい野営訓練を毎年夏と冬にしている。
今年の元旦は能登地震発生から約2時間半後、車両4台に分かれ、被災地へ出発。翌日午前、現地に入った。他の組織よりもいち早く到着したため、隊員だけで捜索・救出を敢行。残念ながら取り残された人は亡くなっていたが、前年の訓練を生かすことができた。
◆プライドを持って
同病院は1991年の雲仙・普賢岳噴火災害で被災し、孤立した経験がある。当時の経験などを基に2012年、被災した孤立地域を支援する組織として同チームは発足した。隊員は医師1人、看護師7人、技師2人、事務員5人(後方支援含む)の計15人。半数は発足時から所属し、4人の女性看護師らが途中で加わった。
出動目安は「震度6」。生存率が大幅に下がるとされる災害発生後72時間までの活動を最重視し、隊長の泉川卓也院長(51)が出動の要否を即座に判断する。これまでに熊本地震(16年)、西日本豪雨(18年)、雲仙土砂災害(21年)など計19回出動した。
泉川院長は「災害チームを持つ病院はあるが捜索・救出までできるチームはない。機動力もあり、孤立地域に強い自負もある」と話し、続けた。「志を同じくして集まってくれた仲間に感謝。このチームは誇りです」。発足時から所属する臨床工学技士、岩永瑞希さん(49)も「(チームの一員として)プライドを持って生きている」と同調した。
◆医療界の異端児
検査技師、時津直史さん(50)は大切な思い出を教えてくれた。「息子が小学生の時、父親をテーマにした作文で『(病院や被災地で頑張る)お父さんのようになりたい』って書いてくれて」。隊員にとって、家族の理解や応援もモチベーションの一つだ。
4人の女性看護師は避難所で丁寧な対応をするなど、その存在感が一層高まる。現場に入る事務員2人は元自衛官と元電気工で、予期せぬ機材トラブルにも迅速に対応。15人の強みを生かし、補い合うことで当初の医療支援から活動の幅が広がってきた。
「自分たちは医療界の異端児」。そう自認する泉川院長の表情からは、医療人としてできる新たな道を切り開く覚悟が見えた。能登の現場で得た教訓は特別なものではなく、日ごろの備えの重要性だと言う。不確実性の高い未来に向け、チームはきょうも準備を続ける。
11月下旬、病院を拠点に大規模災害を想定した訓練が抜き打ちで行われた。各職場で働く隊員を招集。薄暗くなった午後5時過ぎに始まった。駐車場に用意された現場は、がれきの山。崩れた屋根の下に取り残された人を救出するという能登の現場で遭遇したシチュエーションだった。
午後9時ごろ、夕飯を終えると雲仙の山中に移動。道路が寸断され、取り残された負傷者を担架で運び出す訓練で、ヘッドライトの明かりだけを頼りに山道を進んだ。気温3度。霧も深まり、日付が変わるころに終了した。病院に戻って駐車場でテント泊。訓練は3日間続いた。このような2泊3日の厳しい野営訓練を毎年夏と冬にしている。
今年の元旦は能登地震発生から約2時間半後、車両4台に分かれ、被災地へ出発。翌日午前、現地に入った。他の組織よりもいち早く到着したため、隊員だけで捜索・救出を敢行。残念ながら取り残された人は亡くなっていたが、前年の訓練を生かすことができた。
◆プライドを持って
同病院は1991年の雲仙・普賢岳噴火災害で被災し、孤立した経験がある。当時の経験などを基に2012年、被災した孤立地域を支援する組織として同チームは発足した。隊員は医師1人、看護師7人、技師2人、事務員5人(後方支援含む)の計15人。半数は発足時から所属し、4人の女性看護師らが途中で加わった。
出動目安は「震度6」。生存率が大幅に下がるとされる災害発生後72時間までの活動を最重視し、隊長の泉川卓也院長(51)が出動の要否を即座に判断する。これまでに熊本地震(16年)、西日本豪雨(18年)、雲仙土砂災害(21年)など計19回出動した。
泉川院長は「災害チームを持つ病院はあるが捜索・救出までできるチームはない。機動力もあり、孤立地域に強い自負もある」と話し、続けた。「志を同じくして集まってくれた仲間に感謝。このチームは誇りです」。発足時から所属する臨床工学技士、岩永瑞希さん(49)も「(チームの一員として)プライドを持って生きている」と同調した。
◆医療界の異端児
検査技師、時津直史さん(50)は大切な思い出を教えてくれた。「息子が小学生の時、父親をテーマにした作文で『(病院や被災地で頑張る)お父さんのようになりたい』って書いてくれて」。隊員にとって、家族の理解や応援もモチベーションの一つだ。
4人の女性看護師は避難所で丁寧な対応をするなど、その存在感が一層高まる。現場に入る事務員2人は元自衛官と元電気工で、予期せぬ機材トラブルにも迅速に対応。15人の強みを生かし、補い合うことで当初の医療支援から活動の幅が広がってきた。
「自分たちは医療界の異端児」。そう自認する泉川院長の表情からは、医療人としてできる新たな道を切り開く覚悟が見えた。能登の現場で得た教訓は特別なものではなく、日ごろの備えの重要性だと言う。不確実性の高い未来に向け、チームはきょうも準備を続ける。