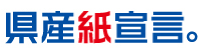上五島地区唯一の分娩(ぶんべん)(出産)施設、長崎県上五島病院(一宮邦訓院長)で分娩の継続が困難になりつつある。助産師が少なく過酷な勤務環境が続いているためだ。来月から分娩休止の可能性もあったが、助産師を新たに確保できたとして当面は回避。だが同病院を運営する県病院企業団は、将来的には医療安全の観点から分娩のみを休止し、産前産後のケアを充実させたいとしている。
一方、分娩機能が島内からなくなれば、若い世代の流出や人口減少に拍車がかかりかねないとの懸念が地元にある。石田信明新上五島町長は「(助産師確保について)企業団の尽力には感謝しているが、引き続き周産期医療体制の維持に努めてほしい」と話している。企業団は「今後も産婦人科は継続する」としている。
企業団によると、少子化の流れで全国の医療機関で分娩数は減少。上五島病院も2018年度は89件だったが、24年度は25件にまで減る見通し。一方、出産年齢の高齢化などに伴い、ハイリスクの妊婦の割合は増加傾向にあり、本土の病院に転院してもらうケースもあるという。
通常分娩には産科医1人と2人の助産師で対応。外来対応も含め医療安全を確保できる勤務シフトを組むには、助産師が8人程度、最低でも6人必要という。しかし、24年度は正規職員が5人しかおらず過酷な勤務が続いており、来月からは4人に減る見込みだった。看護師も不足しており、応援は困難という。
病院側は2月、町と町議会に対し、このまま助産師を確保できなければ、妊婦や赤ちゃんの安全を最優先に考えて分娩だけは本土の医療機関を紹介し、同病院では妊婦健診や産前産後のケアを充実させる方針を伝達。「助産師や看護師は限られた人員で強い使命感を持って働いてきたが、過酷な勤務が続けば離職につながりかねず、町民の健康を守るのも困難になる。苦渋の判断」などと説明した。
その後、町側は再考を求め、企業団も助産師確保に努めた結果、県内の病院から派遣してもらうなどして今春から新たに2人を確保。当面6人体制を維持できることになった。
企業団は「生まれ育った町で出産したいという町民の思いは十分に伝わってきており、分娩をやめたいわけではない。ただ厳しい状況にあることを理解してほしい」としている。
島原市や大村市などの民間医療機関でも分娩を取りやめる動きが相次いでおり、少子化が背景にあるとはいえ、県内で安心して出産できる体制をどう持続させるのかが課題となっている。
一方、分娩機能が島内からなくなれば、若い世代の流出や人口減少に拍車がかかりかねないとの懸念が地元にある。石田信明新上五島町長は「(助産師確保について)企業団の尽力には感謝しているが、引き続き周産期医療体制の維持に努めてほしい」と話している。企業団は「今後も産婦人科は継続する」としている。
企業団によると、少子化の流れで全国の医療機関で分娩数は減少。上五島病院も2018年度は89件だったが、24年度は25件にまで減る見通し。一方、出産年齢の高齢化などに伴い、ハイリスクの妊婦の割合は増加傾向にあり、本土の病院に転院してもらうケースもあるという。
通常分娩には産科医1人と2人の助産師で対応。外来対応も含め医療安全を確保できる勤務シフトを組むには、助産師が8人程度、最低でも6人必要という。しかし、24年度は正規職員が5人しかおらず過酷な勤務が続いており、来月からは4人に減る見込みだった。看護師も不足しており、応援は困難という。
病院側は2月、町と町議会に対し、このまま助産師を確保できなければ、妊婦や赤ちゃんの安全を最優先に考えて分娩だけは本土の医療機関を紹介し、同病院では妊婦健診や産前産後のケアを充実させる方針を伝達。「助産師や看護師は限られた人員で強い使命感を持って働いてきたが、過酷な勤務が続けば離職につながりかねず、町民の健康を守るのも困難になる。苦渋の判断」などと説明した。
その後、町側は再考を求め、企業団も助産師確保に努めた結果、県内の病院から派遣してもらうなどして今春から新たに2人を確保。当面6人体制を維持できることになった。
企業団は「生まれ育った町で出産したいという町民の思いは十分に伝わってきており、分娩をやめたいわけではない。ただ厳しい状況にあることを理解してほしい」としている。
島原市や大村市などの民間医療機関でも分娩を取りやめる動きが相次いでおり、少子化が背景にあるとはいえ、県内で安心して出産できる体制をどう持続させるのかが課題となっている。