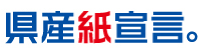今月は認知症月間。急速な高齢化で認知症の人は増加し、高齢者の約3・6人に1人が認知症またはその予備軍とされている。誰もが認知症になり得る時代を迎え、地域のサポートが一層重要になり、長崎県内でも体制づくりが進んでいる。認知症の人、その家族と支援者をつなぐ「チームオレンジ」。国が整備を促進しており、島原市内の取り組みを取材した。
お盆明けの先月16日、介護施設の一角にある喫茶室にお年寄りや夏休み中の子どもたちが集まってきた。地元の市地域包括支援センターの職員やボランティアスタッフが笑顔で迎えた。
総勢約20人のうち認知症本人は4人。三つのテーブルに分かれて自己紹介をした後は、トランプのババ抜きや昔ながらの手遊びを楽しんだり、英語教員だった認知症の女性から子どもたちが英単語を学んだり。時折、大きな笑い声も聞かれ、約1時間半、終始和やかな雰囲気だった。
このチームオレンジ「ことだま」は昨年10月に発足し、月2回活動。コーディネーターの地域包括支援センター職員とともに、一定の講座を受けたボランティアの認知症サポーターが運営を担っている。本人や家族と交流しながら困り事の相談にも乗り、必要な支援につなげる仕組みだ。
ことだまでは通常、編み物や生け花など本人がしたいことをカードに記入してもらい、一緒に活動を楽しんでいる。この日、認知症症状がある夫(77)と一緒に参加した妻(76)は「以前通っていたデイサービスは将棋仲間が亡くなって行かなくなった。自宅にいてもテレビを見ているだけだが、ここで皆さんとふれあい本人も調子がいいようだ」と話した。
国の認知症施策推進大綱は、2025年までに全市町村でチームオレンジなどの仕組みを構築することを目標に掲げる。県によると、23年度末時点で県内21市町のうち9市町で12チームが発足。うち島原市には最多4チームがある。
同市地域包括支援センターの辻敏子所長によると、各公民館で活動する介護予防の自主体操グループや、100以上の事業者・団体が協力する見守りネットワーク協議会の存在など、地域に醸成されている高齢者への理解がチームの発足にも寄与したという。
県は、県内の認知症高齢者は25年に8万4千人と推計するが、認知症予備軍とされる軽度認知障害(MCI)を加えるとさらに膨らむとみられる。今後も各地で研修会や講座を開催するなどして、全市町でチームオレンジの立ち上げを目指す。
お盆明けの先月16日、介護施設の一角にある喫茶室にお年寄りや夏休み中の子どもたちが集まってきた。地元の市地域包括支援センターの職員やボランティアスタッフが笑顔で迎えた。
総勢約20人のうち認知症本人は4人。三つのテーブルに分かれて自己紹介をした後は、トランプのババ抜きや昔ながらの手遊びを楽しんだり、英語教員だった認知症の女性から子どもたちが英単語を学んだり。時折、大きな笑い声も聞かれ、約1時間半、終始和やかな雰囲気だった。
このチームオレンジ「ことだま」は昨年10月に発足し、月2回活動。コーディネーターの地域包括支援センター職員とともに、一定の講座を受けたボランティアの認知症サポーターが運営を担っている。本人や家族と交流しながら困り事の相談にも乗り、必要な支援につなげる仕組みだ。
ことだまでは通常、編み物や生け花など本人がしたいことをカードに記入してもらい、一緒に活動を楽しんでいる。この日、認知症症状がある夫(77)と一緒に参加した妻(76)は「以前通っていたデイサービスは将棋仲間が亡くなって行かなくなった。自宅にいてもテレビを見ているだけだが、ここで皆さんとふれあい本人も調子がいいようだ」と話した。
国の認知症施策推進大綱は、2025年までに全市町村でチームオレンジなどの仕組みを構築することを目標に掲げる。県によると、23年度末時点で県内21市町のうち9市町で12チームが発足。うち島原市には最多4チームがある。
同市地域包括支援センターの辻敏子所長によると、各公民館で活動する介護予防の自主体操グループや、100以上の事業者・団体が協力する見守りネットワーク協議会の存在など、地域に醸成されている高齢者への理解がチームの発足にも寄与したという。
県は、県内の認知症高齢者は25年に8万4千人と推計するが、認知症予備軍とされる軽度認知障害(MCI)を加えるとさらに膨らむとみられる。今後も各地で研修会や講座を開催するなどして、全市町でチームオレンジの立ち上げを目指す。