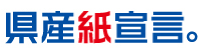長崎市民から「お諏訪さん」と呼ばれ、親しまれる同市の諏訪神社(上西山町)が1625年の創建から今年で400年を迎えた。年間を通じ、節目にふさわしい奉祝行事を展開する。
唐津の修験者で初代宮司となった青木賢清が現在の長照寺(寺町)付近に祭られていた同神社と別々の場所にあった森崎、住吉の2社を合わせ、現在の松森神社(上西山町)の場所に社殿を構えたのが始まりとされる。7柱の神々が鎮座。1648年に現在地に移った。10月の大祭、長崎くんちは全国的に知られ、奉納踊りは国の重要無形民俗文化財に指定されている。
「御鎮座400年」の節目を迎え、吉村政德宮司は「千年の歴史を持つ神社と肩を並べるぐらいの文化の重さ、厚みが諏訪神社にはあり、支えるのはそれを受容する市民。時代は変わっても、根元にあるものの考え方は永劫(えいごう)続くだろうと確信を持っている」と話す。
奉祝行事第1弾は4日午後1時から、境内の舞殿と中庭で開く「諏訪神社日本晴れ~はじまり~」。龍踊や大道芸などさまざまな芸能を奉納する新たな祭りで、「こどもの日」(5日)の長坂のぼり大会と合わせ、春の恒例行事として来年以降も続けていく考え。
奉祝流鏑馬(やぶさめ)(9月)や上五島神楽の奉納(10月)、長崎くんちフォトコンテスト(11月)の催しのほか、同神社の縁者から貴重な掛け軸やべっ甲細工、長崎くんちで宮司が乗り込む輿(こし)の奉納も予定されている。
唐津の修験者で初代宮司となった青木賢清が現在の長照寺(寺町)付近に祭られていた同神社と別々の場所にあった森崎、住吉の2社を合わせ、現在の松森神社(上西山町)の場所に社殿を構えたのが始まりとされる。7柱の神々が鎮座。1648年に現在地に移った。10月の大祭、長崎くんちは全国的に知られ、奉納踊りは国の重要無形民俗文化財に指定されている。
「御鎮座400年」の節目を迎え、吉村政德宮司は「千年の歴史を持つ神社と肩を並べるぐらいの文化の重さ、厚みが諏訪神社にはあり、支えるのはそれを受容する市民。時代は変わっても、根元にあるものの考え方は永劫(えいごう)続くだろうと確信を持っている」と話す。
奉祝行事第1弾は4日午後1時から、境内の舞殿と中庭で開く「諏訪神社日本晴れ~はじまり~」。龍踊や大道芸などさまざまな芸能を奉納する新たな祭りで、「こどもの日」(5日)の長坂のぼり大会と合わせ、春の恒例行事として来年以降も続けていく考え。
奉祝流鏑馬(やぶさめ)(9月)や上五島神楽の奉納(10月)、長崎くんちフォトコンテスト(11月)の催しのほか、同神社の縁者から貴重な掛け軸やべっ甲細工、長崎くんちで宮司が乗り込む輿(こし)の奉納も予定されている。