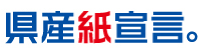地域住民が日ごろの防災や災害時の避難・救助活動に当たる「自主防災組織」。その結成状況を示す活動カバー率で長崎県は74・8%(2024年4月1日現在)と、国内全体の85・4%(同)と比べて10ポイント以上、下回っていることが、総務省消防庁が今月発表した24年版の消防白書で明らかになった。県は現行の総合計画で25年度に80%とする数値目標を掲げているが、ここ数年は微増傾向ながらも70%台前半で伸び悩んでいる。
活動カバー率は全世帯数のうち、自主防災組織が活動範囲とする地域の世帯数の割合を示す。本県では、東日本大震災が起きた2011年に44・5%と、全国の75・8%と比べて30ポイント以上低かった。結成が急がれ、20年には70・1%となった。だが、それ以降は▽21年73・2%(全国84・4%)▽22年73・7%(同84・7%)▽23年74・2%(同85・4%)-と全国との差を縮め切れていない。
阪神大震災(1995年)では、住民が協力し合って初期消火で延焼を防いだり、人命救助に当たったりした事例が数多くみられた。東日本大震災などでも自主防災組織による普段の防災活動を踏まえて住民が適切に避難でき、被害軽減につながった事例がある。本県も「災害時、特に初期段階の対応で、行政の力には限界がある。自分たちの命は自分たちで守るという自助・共助体制が大切」と、自主防災組織を重視する。
本県は諫早大水害(57年)、長崎大水害(82年)、雲仙・普賢岳噴火災害(90年噴火、96年終息宣言)に見舞われている。にもかかわらず、「近年は大きな災害が起きていないため、その怖さや自主防災組織の役割についての認識が薄れてきているのではないか」と、県防災企画課の担当者は懸念する。一方で「あくまで住民の自主的な活動。行政が強制的につくるわけにもいかない」と苦慮している。
活動カバー率は全世帯数のうち、自主防災組織が活動範囲とする地域の世帯数の割合を示す。本県では、東日本大震災が起きた2011年に44・5%と、全国の75・8%と比べて30ポイント以上低かった。結成が急がれ、20年には70・1%となった。だが、それ以降は▽21年73・2%(全国84・4%)▽22年73・7%(同84・7%)▽23年74・2%(同85・4%)-と全国との差を縮め切れていない。
阪神大震災(1995年)では、住民が協力し合って初期消火で延焼を防いだり、人命救助に当たったりした事例が数多くみられた。東日本大震災などでも自主防災組織による普段の防災活動を踏まえて住民が適切に避難でき、被害軽減につながった事例がある。本県も「災害時、特に初期段階の対応で、行政の力には限界がある。自分たちの命は自分たちで守るという自助・共助体制が大切」と、自主防災組織を重視する。
本県は諫早大水害(57年)、長崎大水害(82年)、雲仙・普賢岳噴火災害(90年噴火、96年終息宣言)に見舞われている。にもかかわらず、「近年は大きな災害が起きていないため、その怖さや自主防災組織の役割についての認識が薄れてきているのではないか」と、県防災企画課の担当者は懸念する。一方で「あくまで住民の自主的な活動。行政が強制的につくるわけにもいかない」と苦慮している。