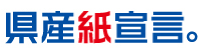長崎県壱岐沖で3人が死亡した医療搬送用ヘリコプター事故を受けて、運航を見合わせていた県のドクターヘリが再開に踏み切る。一方で事故原因の究明は途上。義務化されていないドクターヘリへのフライトレコーダー(飛行記録装置)搭載を求める声もある。
ヘリ事故は毎年発生している。国土交通省によると、2013~22年の10年間に国内で起きた航空事故162件のうちヘリ事故は28件。死亡事故は大型航空機がゼロなのに対し9件30人が亡くなっている。事故全体では原因の8割以上が操縦ミスなど人的要因だ。
ドクターヘリに限れば、16年に神奈川県で着陸時に機体を損傷する事故が起きたものの、01年に国内で導入されて以降、死亡事故は1件もない。
今回事故を起こした医療搬送用ヘリは国の補助を受けて自治体や救命救急センターが配備しているドクターヘリと違い、民間病院の事業として運航。厚生労働省によると、全国で医療用ヘリは61機(ドクターヘリ57、民間機4)が運用されているという。
ドクターヘリは、操縦士に機長として千時間以上の飛行経験を求め、さらに年1回の訓練や従事者に対する能力判定の実施を義務付けるなどし事故防止を図っている。出動要件についても航空法が定める安全飛行基準の「地上視程5千メートル、雲高が地表または水面から300メートル以上」などを順守している。
事故を起こしたヘリを運航していたエス・ジー・シー佐賀航空(佐賀市)の担当者は「安全対策はドクターヘリと同等」と話すが、それでも防げなかった。これに対し原因究明の側面からフライトレコーダーを設置しておくべきだったと指摘する声もある。操縦状況や飛行データなど客観的データを得られるからだ。
ただ、国やドクターヘリ運航会社によると、最大離陸重量3175キロ未満のヘリには設置義務がなく、複数のドクターヘリ運航会社によると6、7人乗りが多い医療搬送用ヘリの大半は未設置。今回の事故機(EC135型、約2980キロ)も搭載していなかった。
設置のネックとなっているのが数千万円規模といわれる費用だ。長崎県のドクターヘリには搭載しているが、昨秋から長期メンテナンス中。運航再開を決めた現在の代替機は一回り小さく、設置義務がないため付けていない。
国交省の運輸安全委員会は、近年は位置情報や操縦室内の映像を記録できる比較的安価で、簡易型のフライトレコーダーも開発されているとして「小型機をはじめ幅広い搭載が望まれる」と指摘する。
ヘリ事故は毎年発生している。国土交通省によると、2013~22年の10年間に国内で起きた航空事故162件のうちヘリ事故は28件。死亡事故は大型航空機がゼロなのに対し9件30人が亡くなっている。事故全体では原因の8割以上が操縦ミスなど人的要因だ。
ドクターヘリに限れば、16年に神奈川県で着陸時に機体を損傷する事故が起きたものの、01年に国内で導入されて以降、死亡事故は1件もない。
今回事故を起こした医療搬送用ヘリは国の補助を受けて自治体や救命救急センターが配備しているドクターヘリと違い、民間病院の事業として運航。厚生労働省によると、全国で医療用ヘリは61機(ドクターヘリ57、民間機4)が運用されているという。
ドクターヘリは、操縦士に機長として千時間以上の飛行経験を求め、さらに年1回の訓練や従事者に対する能力判定の実施を義務付けるなどし事故防止を図っている。出動要件についても航空法が定める安全飛行基準の「地上視程5千メートル、雲高が地表または水面から300メートル以上」などを順守している。
事故を起こしたヘリを運航していたエス・ジー・シー佐賀航空(佐賀市)の担当者は「安全対策はドクターヘリと同等」と話すが、それでも防げなかった。これに対し原因究明の側面からフライトレコーダーを設置しておくべきだったと指摘する声もある。操縦状況や飛行データなど客観的データを得られるからだ。
ただ、国やドクターヘリ運航会社によると、最大離陸重量3175キロ未満のヘリには設置義務がなく、複数のドクターヘリ運航会社によると6、7人乗りが多い医療搬送用ヘリの大半は未設置。今回の事故機(EC135型、約2980キロ)も搭載していなかった。
設置のネックとなっているのが数千万円規模といわれる費用だ。長崎県のドクターヘリには搭載しているが、昨秋から長期メンテナンス中。運航再開を決めた現在の代替機は一回り小さく、設置義務がないため付けていない。
国交省の運輸安全委員会は、近年は位置情報や操縦室内の映像を記録できる比較的安価で、簡易型のフライトレコーダーも開発されているとして「小型機をはじめ幅広い搭載が望まれる」と指摘する。