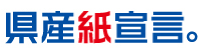長崎県内の自治体を対象に実施した線状降水帯への対応などを尋ねるアンケート結果について、全国各地の防災タイムライン策定の第一人者で、アンケートを監修した東京大大学院情報学環総合防災情報研究センター客員教授の松尾一郎氏に、各自治体の対応状況に対する意見を聞いた。
松尾氏によると、線状降水帯が要因の大雨は昨年、全国で34回あった。このうち死者、重軽傷者の発生は14回に上り、「2回に1回は人的被害が起こりうる災害といえる」という。
松尾氏は各自治体の回答について「防災情報としての認知度は高く、危機感の醸成にも寄与している」と評価。しかし「(対応は)まだ情報の内容や、どのようなことが起こりうるかの想像が不十分。的確な対応に結びつている自治体は少ないようだ」とし、未経験の情報に対する不安と難しさが明らかになったと分析。
半日前予測情報が発表された場合、避難指示や緊急安全確保など最高度の対応を住民に求めている自治体が多く「むしろ夜間や休日の縛りがなければ、半日の猶予時間があるため、要支援者も含めて高齢者避難を早めに促し、市民の不安を解消する方策も考えておきたい」と指摘する。
線状降水帯がいきなり発生した場合も同様だ。気象庁が定義する線状降水帯が発生した時の大雨を想像すると、すでに道路は冠水していて、中小の河川は氾濫している可能性が高い。松尾氏は「この時、高齢者に水平避難を求めるのはありえない」と強調。既に警報級の大雨と考えられるため、その前の段階で避難所を開き、避難を促すことが必要とし「逃げ遅れた場合は、垂直避難を求めるなどの防災行動を考えておくことが命を守る防災につながる」と提起する。
防災行動計画を時系列でまとめる「タイムライン防災」を10年前から全国の市町村や自治会などに普及してきた松尾氏。あらかじめ起こりうる災害を理解し、防災行動を関係者が話し合って合意するタイムラインが、線状降水帯のような突発災害でも命を守ると呼びかける。「長崎県のように土砂災害や中小の河川の氾濫のリスクが高い地域こそ、市町村タイムラインや自治会単位のコミュニティタイムラインは必須だと思っている」
松尾氏によると、線状降水帯が要因の大雨は昨年、全国で34回あった。このうち死者、重軽傷者の発生は14回に上り、「2回に1回は人的被害が起こりうる災害といえる」という。
松尾氏は各自治体の回答について「防災情報としての認知度は高く、危機感の醸成にも寄与している」と評価。しかし「(対応は)まだ情報の内容や、どのようなことが起こりうるかの想像が不十分。的確な対応に結びつている自治体は少ないようだ」とし、未経験の情報に対する不安と難しさが明らかになったと分析。
半日前予測情報が発表された場合、避難指示や緊急安全確保など最高度の対応を住民に求めている自治体が多く「むしろ夜間や休日の縛りがなければ、半日の猶予時間があるため、要支援者も含めて高齢者避難を早めに促し、市民の不安を解消する方策も考えておきたい」と指摘する。
線状降水帯がいきなり発生した場合も同様だ。気象庁が定義する線状降水帯が発生した時の大雨を想像すると、すでに道路は冠水していて、中小の河川は氾濫している可能性が高い。松尾氏は「この時、高齢者に水平避難を求めるのはありえない」と強調。既に警報級の大雨と考えられるため、その前の段階で避難所を開き、避難を促すことが必要とし「逃げ遅れた場合は、垂直避難を求めるなどの防災行動を考えておくことが命を守る防災につながる」と提起する。
防災行動計画を時系列でまとめる「タイムライン防災」を10年前から全国の市町村や自治会などに普及してきた松尾氏。あらかじめ起こりうる災害を理解し、防災行動を関係者が話し合って合意するタイムラインが、線状降水帯のような突発災害でも命を守ると呼びかける。「長崎県のように土砂災害や中小の河川の氾濫のリスクが高い地域こそ、市町村タイムラインや自治会単位のコミュニティタイムラインは必須だと思っている」