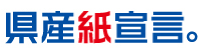病になっても住み慣れた家で最期まで暮らしてほしい-。そんな思いを胸に、在宅診療とみとりを専門としたクリニックを、長崎県北松佐々町に初めて開業した人がいる。とみやす在宅クリニックの冨安志郎さん(59)。患者とその家族に寄り添いながら、最期を見届けている。
「お体どうですか」。冨安さんは、昨年11月に亡くなった敦賀一彦さん(享年80歳)の妻、節子さん(78)宅を看護師と一緒に訪問し、優しく声を掛けていた。問診後、電子カルテで薬のデータを訪問薬剤師に送っていた。
一彦さんは直腸がんなどを患っていた。何度も手術し、病院で治療する手だてが無くなっていた。「近所のざわめき、テレビや台所でご飯を準備している音…。暮らしの中で自然に最期を迎えてほしい」。そう考えた節子さんは昨年8月ごろ、冨安さんに治療を依頼した。
冨安さんは寝たきりになった一彦さんの様子を休日でも見に来てくれたり、節子さんに声を掛けてくれたりした。一彦さんは亡くなったとき、今まで見たことのないような穏やかな顔をしていたという。節子さんは「細やかに夫の体の状態を見てくれて、私にも寄り添ってくれた。本当にありがたい」とほほ笑んだ。
★
冨安さんは、福岡県出身。佐賀医科大(現・佐賀大医学部)を卒業後、長崎大医学部の麻酔科に入局した。1996年に身体的な痛みを取り除くペインクリニック外来を担当。そこで、病気に伴う心や体など多岐にわたる痛みを和らげる緩和ケアを知った。がん患者だけでなく、重い病の治療をしている患者の苦痛を和らげるため、緩和ケアを学び、2003年には長崎大学病院での緩和ケアチーム発足に携わった。
在宅診療の現場にも足を運ぶように。そこでは病院とは異なり、患者が穏やかな表情だったことに気が付いた。その人らしい暮らしを少しでも長く続けてもらえる仕事にやりがいを感じ、在宅医になることを考え始めた。
佐賀県の病院で働いていた時、長崎県北からの患者が多くいた。中には最期は家に帰りたくても、みとる医者がおらず、入院を余儀なくされた人も。長崎市に比べ、終末期をみとる医師や診療所が不足している状況を目の当たりにした。
「何とかしなければ」。高齢社会の真っただ中で、県北での在宅の受け皿をつくることが喫緊の課題だと痛感した。自身の年齢を考えると働けるのは残り10年程度。「自分が受け皿になろう」。そう決意した。昨年4月、松浦市や平戸市にも訪問が可能な佐々町で開業した。 現在では、約40人の患者を受け持ち、1日に平均7~8軒を巡回。開業後、既に2万5千キロを走行した。コロナ禍で、病院の面会が制限されているため、最期は家でみとりたいとの相談も受けるという。
「『医者がいないから、家で亡くなれない』と言わせない地域にしたい」。冨安さんはそう意気込み、患者の元に足早に向かった。