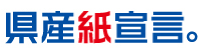76年前の8月9日。長崎市松山町の上空でさく裂した原子爆弾が、多くの人々の営みを焼き尽くした。ある11歳の少女もまた肉親を、健やかな体を、そして希望を奪われた。それでも絶望の淵からはい上がり、新たな家族を築き、懸命に守ってきた。その少女はもうすぐ米寿を迎える。「この苦しみは、私たちだけで終わりに」-。長崎市の被爆者、荒川佐代子さん(87)の声に耳を傾けたい。
1945年夏。山里国民学校(現在の長崎市立山里小)の6年生だった。その数年前、ひとり親の母親は佐代子さんと姉を連れ、3人の子がいる男性と再婚。さらに弟と妹も生まれていた。継父の母親も含め、にぎやかな10人家族だった。
疎開先の諫早から長崎に戻って間もない8月9日。高尾町の母の実家で、幼い弟を抱き、縁側にいた。
午前11時2分。「ピカーっとした」。光は覚えている。気が付くと倒れた家の下敷き。近くにいた伯父に助け出されたが、背中や右腕は熱線で焼けただれた。弟は家の中で見つかり、畑仕事をしていた母も無事。爆心地から約1.2キロだったが、より爆心地に近い橋口町の自宅にいた実姉ら4人は、このとき爆死した。
数日を防空壕(ごう)で過ごし、母や継父、弟と共に諫早の親類宅に身を寄せた。母は毎日のように長崎へ通い、姉たちの骨を探したが、「体がきつい」と漏らして1カ月ほどで急死。弟が原因も分からず亡くなったのも同じころだ。
血のつながった家族は、みんな逝った。「その瞬間ね、なーんも思っとらんとですよ。『なんで死んだとかな』くらい。でも後から…寂しかった」。うつむく佐代子さんの声が震えた。
その後、一人残された佐代子さんを異変が襲う。髪は抜け、「喉が腐る」ような症状が現れた。喉は異臭を放ち、声が出ず、痛かった。諫早の親類宅では一室に隔離され、ときどき食事が運ばれてくるだけ。守ってくれる母も、姉も、もういない。孤独だった。
翌春、長崎の伯父夫妻の養子に迎えられた。新しい父と母、9歳下の妹ができた。家業は製材・建築業で食事に困ることもなく「とても良くしてくれた」。
それでも消えない孤独感。母や姉が眠る高尾町の墓地に何度も足を運んだ。「どうして私を独り残して逝ったの」-。何度も何度も墓石をたたいて、泣いた。
24歳で結婚。夫の勇さんも被爆者だった。佐代子さんは右腕、勇さんは左腕にやけどの痕があった。「とても優しい人」。何もかも奪われた「あの日」から、初めて幸せを感じた。
佐代子さんは50代のころ、相次いで左右の乳がん手術を受けた。勇さんは仕事帰りに毎晩、病院を見舞ってくれた。原爆の記憶を背負う2人は寄り添い、共に生きた。2012年。84歳で生涯を閉じる勇さんに、感謝を伝えた。「良くしてくれたね、ありがとう」
佐代子さんは今、長崎市内の老人ホームで静かに暮らす。長女敦子さん(55)が週に2、3回は顔を見せる。「うれしいですよ。でも帰った後は寂しくて」。新型コロナ禍で面会は制限され、ゆっくり話す時間はない。家族と過ごす時間の尊さを、あらためて思う。
「(敦子さんも)来てくれます。主人も良い人だった。生きててよかった」。家族の喪失と再生。あの日から76年、生き抜いてきた。