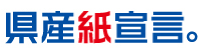かつて海だった場所には城が築かれ、やがて高校や文化会館に姿を変えた。石垣と堀だけが、ほぼ当時のまま残る。長崎県五島市中心部の史跡、福江城跡。本丸跡に建つ県立五島高の生徒たちは毎朝、城門をくぐって“登城”する。
城郭史に詳しい同市の郷土史家、中村眞由美さん(67)によると、石垣など基礎部分の多くは江戸時代初期、20年をかけて海岸を埋め立て築かれた。その上に建てられた陣屋は、江戸末期の1863年に福江城が完成するまでの200年以上、五島藩の城として使われたという。
福江城は三方を海に囲まれた「海城」で、難工事を要した。中村さんは、それでも五島藩がこの場所に城を築いた大きな理由が、幕府に与えられた「役割」にあるとみる。それは、東シナ海を行き来する国内外の船を見張る「船見役」。海に面しているため、すぐに船を出して外国船を遠ざけたり、漂着船を調べたりすることができたという。
今では三方の海も埋め立てられ、市民の教育や文化の拠点に。それでも石垣と堀に囲まれた威容から、「防御力が日本一高い高校」と自負する五島高生もいる。歴史上の役割を知ると、あながち的外れでもなさそうだ。
【動画】五島・福江城跡 石垣と堀が囲む高校
長崎新聞 2020/11/04 [12:00] 公開