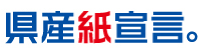江戸時代の大災害「島原大変」(1792年)の津波で亡くなった人たちを弔う長崎県島原市中堀町の市指定史跡「宝篋印塔(ほうきょういんとう)型 流死供養塔」が、市道拡幅に伴い移設されることが29日までに分かった。市教委が市文化財保護審議会(会長=根井浄・元龍谷大教授)に諮問し、認められた。移設は2027年度末ごろの見込み。同市内で指定史跡が移設されるのは初めてとなる。
市教委文化財課などによると、供養塔がある中堀町水頭(みずがしら)地区は、島原大変当時は海辺で、多くの犠牲者の遺体が漂着した。供養塔は雲仙の寺院住職が豪商らの支援を受け1793年に建立。高さ約3メートルの石碑には、豪商の身内ら溺死した105人の俗名と戒名などが刻まれている。
市は交通量増加のため、市道堀町縦線(約550メートル)を拡幅しており、2027年度内の完成を予定している。供養塔は、拡幅した際の車道の一部にかかる見通し。地元の町内会からは、供養塔が車からの視界を遮り歩行者が危険として、移設を望む要望書が市教委に出されていた。
島原大変から半世紀後の1842年に写しが描かれた「島原城下図」(九州大学附属図書館蔵)には、江東寺(中堀町)の近くに供養塔が記されていて、市教委は供養塔の位置が当時と変わっていないとみている。供養塔を移設すると、島原大変の犠牲者が漂着した位置を示す歴史的価値が損なわれる恐れがあった。
市教委は「歩行者の安全性確保の観点から移設の要望がある」として2月18日の市文化財保護審議会に移設の可否を諮問。同審議会は「歩行者の安全や社会情勢上、やむを得ない」として移設を認めた。一方「現在地からそう遠くないところに移設してほしい」との意見も付けた。
市教委文化財課によると1985年、江東寺近辺の市道を拡幅した際に、文化財に指定されていない「溺死無縁塔」を同寺墓地に移設したが、跡地から多数の人骨が出土したという。担当者は「供養塔を移設する前に丁寧に埋蔵物調査を行いたい。移設先は協議中で現時点では決まっていない」と話している。
市道路課は「移設後は、流死供養塔があった場所が分かるよう現地にプレートをはめ込むなどの対応を考えたい」としている。
市教委文化財課などによると、供養塔がある中堀町水頭(みずがしら)地区は、島原大変当時は海辺で、多くの犠牲者の遺体が漂着した。供養塔は雲仙の寺院住職が豪商らの支援を受け1793年に建立。高さ約3メートルの石碑には、豪商の身内ら溺死した105人の俗名と戒名などが刻まれている。
市は交通量増加のため、市道堀町縦線(約550メートル)を拡幅しており、2027年度内の完成を予定している。供養塔は、拡幅した際の車道の一部にかかる見通し。地元の町内会からは、供養塔が車からの視界を遮り歩行者が危険として、移設を望む要望書が市教委に出されていた。
島原大変から半世紀後の1842年に写しが描かれた「島原城下図」(九州大学附属図書館蔵)には、江東寺(中堀町)の近くに供養塔が記されていて、市教委は供養塔の位置が当時と変わっていないとみている。供養塔を移設すると、島原大変の犠牲者が漂着した位置を示す歴史的価値が損なわれる恐れがあった。
市教委は「歩行者の安全性確保の観点から移設の要望がある」として2月18日の市文化財保護審議会に移設の可否を諮問。同審議会は「歩行者の安全や社会情勢上、やむを得ない」として移設を認めた。一方「現在地からそう遠くないところに移設してほしい」との意見も付けた。
市教委文化財課によると1985年、江東寺近辺の市道を拡幅した際に、文化財に指定されていない「溺死無縁塔」を同寺墓地に移設したが、跡地から多数の人骨が出土したという。担当者は「供養塔を移設する前に丁寧に埋蔵物調査を行いたい。移設先は協議中で現時点では決まっていない」と話している。
市道路課は「移設後は、流死供養塔があった場所が分かるよう現地にプレートをはめ込むなどの対応を考えたい」としている。