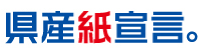長崎県の壱岐、対馬、五島の3市と新上五島町の文化財で構成する日本遺産「国境の島 壱岐・対馬・五島 古代からの架け橋」は今月、認定10年を迎えた。認定後、情報発信や組織整備が進んだ一方、誘客や地元への浸透には課題もある。県は本年度、市町と連携して記念事業を展開し、認知度向上に向け、てこ入れを図る。
日本遺産は文化庁が2015年に創設。地域の歴史や伝統文化を「ストーリー」としてまとめ、国内外に発信することで、地域活性化を図る。「国境の島-」は認定第1号の18件に選ばれた。4市町の文化財計30件で構成。日本本土と大陸の間に位置する島々が、古代から交通の要衝となり、交流・交易拠点の役割を担った歴史を伝えている。
20年度以降は、総括評価・認定審査が導入され、成果や取り組みが乏しい地域は再審査や認定取り消しの対象になる。「国境の島-」はこれまで2度審査され、いずれも認定が継続。24年度の前回審査では、地元の組織整備や事業計画の具体性などが評価された一方、観光客数や「地域の文化に誇りを感じる住民の割合」で目標の未達成が指摘された。
県文化振興・世界遺産課によると、認定後、構成資産がある各市町では案内板設置や多言語化、旅行商品の造成、ガイド育成などが進んだ。観光客数は新型コロナウイルス禍の影響を受けたが、近年は回復傾向。各市町の拠点施設となる博物館や資料館の入館者数は、認定前より増加した。
記念事業は、インバウンド(訪日客)を含めた誘客とシビックプライド(地域住民の誇り)醸成を見据え、情報発信に力を入れる。JR長崎駅在来線改札口内で6月20日まで、構成文化財の一つで、原の辻遺跡(壱岐市)の出土品「人面石」の複製を展示。公式インスタグラムも新たに開設し、構成文化財の紹介と共に、各市町の自然や食などの観光情報も発信する。
今後は、地元市町での講演会や展示会、構成文化財を巡るツアーなども計画。観光客の旅程に同行し、各離島を共に巡りながら案内する「国境の島ナビゲーター」の育成にも取り組む。同課の担当者は「10周年を機に、日本遺産と国境の島の認知度をさらに高める。にぎわいが地元住民の愛着を生み、さらなる地元からの情報発信を促すといった好循環につなげたい」としている。
日本遺産は文化庁が2015年に創設。地域の歴史や伝統文化を「ストーリー」としてまとめ、国内外に発信することで、地域活性化を図る。「国境の島-」は認定第1号の18件に選ばれた。4市町の文化財計30件で構成。日本本土と大陸の間に位置する島々が、古代から交通の要衝となり、交流・交易拠点の役割を担った歴史を伝えている。
20年度以降は、総括評価・認定審査が導入され、成果や取り組みが乏しい地域は再審査や認定取り消しの対象になる。「国境の島-」はこれまで2度審査され、いずれも認定が継続。24年度の前回審査では、地元の組織整備や事業計画の具体性などが評価された一方、観光客数や「地域の文化に誇りを感じる住民の割合」で目標の未達成が指摘された。
県文化振興・世界遺産課によると、認定後、構成資産がある各市町では案内板設置や多言語化、旅行商品の造成、ガイド育成などが進んだ。観光客数は新型コロナウイルス禍の影響を受けたが、近年は回復傾向。各市町の拠点施設となる博物館や資料館の入館者数は、認定前より増加した。
記念事業は、インバウンド(訪日客)を含めた誘客とシビックプライド(地域住民の誇り)醸成を見据え、情報発信に力を入れる。JR長崎駅在来線改札口内で6月20日まで、構成文化財の一つで、原の辻遺跡(壱岐市)の出土品「人面石」の複製を展示。公式インスタグラムも新たに開設し、構成文化財の紹介と共に、各市町の自然や食などの観光情報も発信する。
今後は、地元市町での講演会や展示会、構成文化財を巡るツアーなども計画。観光客の旅程に同行し、各離島を共に巡りながら案内する「国境の島ナビゲーター」の育成にも取り組む。同課の担当者は「10周年を機に、日本遺産と国境の島の認知度をさらに高める。にぎわいが地元住民の愛着を生み、さらなる地元からの情報発信を促すといった好循環につなげたい」としている。