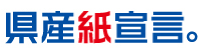2年前の3月13日。1本の電話から人生が一変した。「貧血が緊急搬送レベルです」。村川美詠さん(61)=長崎県諫早市=は体調がすぐれず、2日前にかかりつけ医を受診した。仕事を抜けて病院に行くと、市内の総合病院に向かうよう言われた。そこで告げられたのは「白血病の疑い」。その日のうちに長崎大学病院(長崎市)に入院した。
診断は急性リンパ性白血病。「自分のことなのに実感が湧かなかった」。仕事の引き継ぎをしたり、友人とのランチの約束をキャンセルしたり。「還暦を迎える年なのに、両親に何と説明しようか」。涙が頬を伝った。
諫早市出身。1986年、市職員に採用され、職員研修や男女共同参画などを担当。市職員や他県の公務員との勉強会、市内の異業種の女性でつくる「諫早もりあげガールズ」で地域活性化に奔走してきた。
2022年4月、健康保険部長に昇進。05年3月の1市5町の合併後、同市2人目の女性部長。「せっかくのチャンス。庁内の大事なことを決める場に女性がいないと、女性だけではなく若い人の意見も反映されにくくなる」。そう思い、五つの課・室を率いた。
これまで大病を患った経験はなかった。頭も心も整理できないまま、入院10日目から本格的な抗がん剤治療に入った。吐き気や食欲減退、高熱、身体のだるさに苦しみ、髪の毛はほとんど抜けた。骨髄移植を決意したが、検査結果は「移植困難」。その後、自身のT細胞を使い、免疫反応でがん細胞を死滅させるビーリンサイト治療を開始。一進一退の病状に「死を意識する日々」が続いた。
入院から半年後。病床で好きな本が読めるようになり、友人たちに病状を伝えた。その年の年末、自身の交流サイトで闘病生活を明かした。その後、1カ月余りの入院と50日ほどの退院を繰り返し、血液の状態も少しずつ正常値に近づいた。
医師から「(寛解状態となり)最後の入院治療」を告げられた昨年秋、市職員を辞める決意をした。休職期間を終え、職場復帰を考えたが、1年半以上のブランクとフルタイムで働くための体力的な自信が持てなかった。
病気になって気付いたのは「何げない日常が続くことが一番の幸せ」。1年8カ月、延べ383日間の入院生活を支えてくれた夫(63)、長女(32)、父(92)、母(86)との時間を大事にしたいと思った。昨年末、38年間の市職員生活に別れを告げた。
2月初め、大村市内の会議室。村川さんの笑い声が響く。会議などで役立つファシリテーション講座の講師。参加者の意見をホワイトボードに書きながら、活発に意見を交わす会議進行の方法を伝えていた。
3月、進学や就職、転職、定年退職など、さまざまな旅立ちを迎える人がいる。少しだけ早く新しいステージに進んだ村川さん。「多様性が叫ばれる時代、自分の指示がハラスメントと思われないかなどと、多くのリーダーは悩んでいる。対話の文化と学び合いの価値を伝え、業務の“見える化”が進むお手伝いをしたい」
今年に入り、リーダーシップ研修などを行う「みえるか工房」を起業。個人事業主「1年生」の春は始まっている。
診断は急性リンパ性白血病。「自分のことなのに実感が湧かなかった」。仕事の引き継ぎをしたり、友人とのランチの約束をキャンセルしたり。「還暦を迎える年なのに、両親に何と説明しようか」。涙が頬を伝った。
諫早市出身。1986年、市職員に採用され、職員研修や男女共同参画などを担当。市職員や他県の公務員との勉強会、市内の異業種の女性でつくる「諫早もりあげガールズ」で地域活性化に奔走してきた。
2022年4月、健康保険部長に昇進。05年3月の1市5町の合併後、同市2人目の女性部長。「せっかくのチャンス。庁内の大事なことを決める場に女性がいないと、女性だけではなく若い人の意見も反映されにくくなる」。そう思い、五つの課・室を率いた。
これまで大病を患った経験はなかった。頭も心も整理できないまま、入院10日目から本格的な抗がん剤治療に入った。吐き気や食欲減退、高熱、身体のだるさに苦しみ、髪の毛はほとんど抜けた。骨髄移植を決意したが、検査結果は「移植困難」。その後、自身のT細胞を使い、免疫反応でがん細胞を死滅させるビーリンサイト治療を開始。一進一退の病状に「死を意識する日々」が続いた。
入院から半年後。病床で好きな本が読めるようになり、友人たちに病状を伝えた。その年の年末、自身の交流サイトで闘病生活を明かした。その後、1カ月余りの入院と50日ほどの退院を繰り返し、血液の状態も少しずつ正常値に近づいた。
医師から「(寛解状態となり)最後の入院治療」を告げられた昨年秋、市職員を辞める決意をした。休職期間を終え、職場復帰を考えたが、1年半以上のブランクとフルタイムで働くための体力的な自信が持てなかった。
病気になって気付いたのは「何げない日常が続くことが一番の幸せ」。1年8カ月、延べ383日間の入院生活を支えてくれた夫(63)、長女(32)、父(92)、母(86)との時間を大事にしたいと思った。昨年末、38年間の市職員生活に別れを告げた。
2月初め、大村市内の会議室。村川さんの笑い声が響く。会議などで役立つファシリテーション講座の講師。参加者の意見をホワイトボードに書きながら、活発に意見を交わす会議進行の方法を伝えていた。
3月、進学や就職、転職、定年退職など、さまざまな旅立ちを迎える人がいる。少しだけ早く新しいステージに進んだ村川さん。「多様性が叫ばれる時代、自分の指示がハラスメントと思われないかなどと、多くのリーダーは悩んでいる。対話の文化と学び合いの価値を伝え、業務の“見える化”が進むお手伝いをしたい」
今年に入り、リーダーシップ研修などを行う「みえるか工房」を起業。個人事業主「1年生」の春は始まっている。