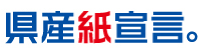長崎県佐世保市鹿子前町の九十九島水族館(海きらら)は、平戸市の田平港で採集したクラゲが日本初記録となる「カンザシスズフリクラゲ」であることを発表した。研究成果を今月、論文として報告した。
カンザシスズフリクラゲは、2000年にパプアニューギニアで採集された個体が新種とされている。生息域や詳しい生態などは明らかになっていない。
海きららのスタッフは21年8月、田平港で採集。同年11月に静岡でも確認された。これらについて、海きららと黒潮生物研究所(高知県)、新江ノ島水族館(神奈川県)が共同で論文を執筆。スイスの学術雑誌「taxonomy」に掲載された。
傘の直径が約1・5ミリの小型種。2本の触手があり、それに毒針の刺胞塊がある。ポリプと呼ばれる部分が、髪留めのかんざしのように見えることが、和名の由来となっている。海きららが採集した個体は、国立科学博物館(東京)に標本として収蔵されている。海きららには、特徴を紹介するパネルが設置されている。
海きららは06年から九十九島周辺でクラゲの調査を進め、約150種を確認。常時約20種を展示するなど、繁殖を含めた研究に力を入れている。
飼育員の野添裕一さん(41)は「新種が見つかるのは海が豊かな証拠。多くの人が興味を持つよう、クラゲのいろんな情報を発信していきたい」と話している。
カンザシスズフリクラゲは、2000年にパプアニューギニアで採集された個体が新種とされている。生息域や詳しい生態などは明らかになっていない。
海きららのスタッフは21年8月、田平港で採集。同年11月に静岡でも確認された。これらについて、海きららと黒潮生物研究所(高知県)、新江ノ島水族館(神奈川県)が共同で論文を執筆。スイスの学術雑誌「taxonomy」に掲載された。
傘の直径が約1・5ミリの小型種。2本の触手があり、それに毒針の刺胞塊がある。ポリプと呼ばれる部分が、髪留めのかんざしのように見えることが、和名の由来となっている。海きららが採集した個体は、国立科学博物館(東京)に標本として収蔵されている。海きららには、特徴を紹介するパネルが設置されている。
海きららは06年から九十九島周辺でクラゲの調査を進め、約150種を確認。常時約20種を展示するなど、繁殖を含めた研究に力を入れている。
飼育員の野添裕一さん(41)は「新種が見つかるのは海が豊かな証拠。多くの人が興味を持つよう、クラゲのいろんな情報を発信していきたい」と話している。