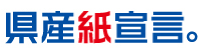長崎市は27日、市動物愛護管理センターによる猫の殺処分数が、2024年度は初めてゼロになるとの見通しを発表した。同センターは主な要因として、殺処分の対象となりやすい生まれたての子猫を育てるミルクボランティア制度が本年度始まったことを挙げた。
同センターはけがをして自力で生活できないなどの猫を収容。収容可能数を超えた場合などは、殺処分している。
環境省の集計によると、22年度の同市の猫の殺処分数201匹(自然死など88匹を含む)は全国の中核市でワースト3位だった。人の手による殺処分がゼロとなった背景には、野良猫の不妊化を進めて地域住民らが餌やりや猫用トイレを管理する地域猫活動や、市の「まちねこ不妊化推進事業」など官民の取り組みなどがあるという。行政側が動物愛護の観点から引き取りを拒否できる要件が法改正で追加されたことも殺処分が減った要因とみられる。
一方、自治体が環境省へ届け出る殺処分数には収容後に病死するなどの自然死も含まれ、本年度はこれまでに30匹。同センターは「ミルクボランティア制度の充実や、譲渡の推進などをさらに進め、不幸な猫を減らしたい」としている。
鈴木史朗市長は27日の定例記者会見で「殺処分ゼロを継続できるよう、ボランティアや地域の皆さんと連携を深め、しっかり取り組む」と述べた。
同センターはけがをして自力で生活できないなどの猫を収容。収容可能数を超えた場合などは、殺処分している。
環境省の集計によると、22年度の同市の猫の殺処分数201匹(自然死など88匹を含む)は全国の中核市でワースト3位だった。人の手による殺処分がゼロとなった背景には、野良猫の不妊化を進めて地域住民らが餌やりや猫用トイレを管理する地域猫活動や、市の「まちねこ不妊化推進事業」など官民の取り組みなどがあるという。行政側が動物愛護の観点から引き取りを拒否できる要件が法改正で追加されたことも殺処分が減った要因とみられる。
一方、自治体が環境省へ届け出る殺処分数には収容後に病死するなどの自然死も含まれ、本年度はこれまでに30匹。同センターは「ミルクボランティア制度の充実や、譲渡の推進などをさらに進め、不幸な猫を減らしたい」としている。
鈴木史朗市長は27日の定例記者会見で「殺処分ゼロを継続できるよう、ボランティアや地域の皆さんと連携を深め、しっかり取り組む」と述べた。