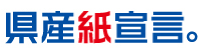長崎市に原爆が投下された3日後、4歳上の次姉と疎開していた佐賀市の親戚宅に父と次兄が訪ねてきた。父の首には白い布で包まれた箱がぶら下がっている。爆心地に近い浜口町の自宅にいた母と長姉が死んだ、と聞かされた。当時7歳。状況を理解できていたかわからないが、ただ悲しくてみんなで泣いた。
父によると、母は昼食を用意していたのか、炊事場の近くに倒れていた。長姉は外で隣家の塀の下敷きに。上半身は焼けていたが、残っていたもんぺの模様で分かったという。自らの手で火葬し、遺骨を持って来ていた。
8月15日に家族4人で長崎へ戻った。父と次兄が勤務していた川南工業香焼造船所が、香焼町に家族で暮らす家をあてがってくれた。19日、城山国民学校でコメの配給があると聞き、父と次姉と一緒に船で大波止に渡り、そこから歩いて向かい、焼け野原となった自宅付近にも寄った。長崎医科大付属病院の2本の煙突は1本がくの字に曲がっている、山王神社の片足鳥居がはっきりと近くに見える、そんな記憶が残っている。
学校の近くでは、あちこちに白骨の山ができていた。6月まで通っていた学校。その変わり果てた姿を前にして、長崎にいたら間違いなく自分も死んでいた、友達もみんな死んでしまったのだろう、との思いを抱いた。
コメをもらった後、街を見渡せる近くの土手に腰を下ろし、持ってきた昼食を食べることにした。だが、眼下から乾いた空気に乗って、焼けた人骨の臭いが漂ってくる。とても食欲は湧かず、3人とも一口も食べられなかった。
香焼町には当時、捕虜収容所があり、終戦後、米軍の飛行機が収容所を目がけ、落下傘で救援物資を投下していた。赤、青、緑…。家から見えた、次々と落ちていくカラフルな落下傘がきれいだった。
それからの生活で原爆のことに触れる機会は少なく、2人の息子にも伝えてこなかった。10年ほど前、小学生の孫の宿題で初めて体験を語ることに。多少のショックを受けた様子だったが、目に涙をためながら受け止めてくれた。
その出来事を機に体験記をつづり、他の孫たちにも思いを託した。「ぜったいに戦争をしてはいけないというおじいちゃんの思いを皆さんに引き継いでもらいたい。(文章を読んで)平和な国をつくろうと思ってくれたらうれしいです」、と。
◎私の願い
核兵器は人類の滅亡を招くことを知りながら手放そうとしない核保有国のエゴと、核廃絶を進められない国連の無力さに憤りさえ感じる。将来の子どもたちのため、一日も早く地球から核がなくなることを願っている。